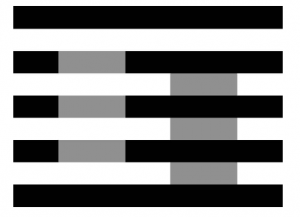考える力を鍛えるには?
#8 柱に亀裂を入れると長持ちする。
ひょんなことから不動産業で活躍する F さんと子供のつながりでお話を聞くことができました。
在来工法のすごいところは柱に亀裂を入れること。
柱が受けるさまざまな衝撃を亀裂によってできた隙間が吸収するのです。
結果的にその建物は長持ちするのです。
現代の効率的なツーバイフォー工法で亀裂があれば、間違いなく即クレームの対象となるでしょう。
表面的なことにしか興味を示さない。
奥深い事象を洞察する思慮深さが欠けているのではないでしょうか?
宮大工の知恵はそうした奥深い洞察があったからなのでしょう。
なぜこの建物は壊れず、この建物は壊れたのだろうと原因やプロセスを考える力が間違いなくあったはずです。
長い時間を経由して初めて分かることが世の中たくさんあるのです。
現代で ”はやり” の行動様式としては、時間術、仕事術などで表現されるように
如何に効率的に再現性のあるフォーマトを作れるか
それにより空いた時間でクリエイティブな事をしましょう。
というような考え方だと感じます。
ただし現実は空いた時間で更に効率的な何かを追い求めているような気がします。
表面的、短絡的に考えるのではなく、じっくりと腰を据えて考える時間が自分も含めて現代人には欠けているのではないでしょうか?
伝統を引き継ぐ
今年は20年に1度の伊勢神宮の式年遷宮の年でした。
式年遷宮とは日本誕生の生みの親である神様を祀る伊勢神宮の建物を20年に1度
敢えて取り壊し再度建て直す行事です。
効率や経済合理性だけを考えたら
なんと無駄なことだと思うでしょう。
ただし視点を ”伝統を引き継ぐ” としてみたら
先人の功績を自らが習得するには、「習って、真似て、捨ててみる」ことが必要となります。
守破離という考えが共感を呼ぶのも、まだ日本人の心の奥底に眠るDNA
白黒はっきりさせる事よりも曖昧モコ的な結論を好む。
誰か一人の天才を崇拝するより
皆が平均的に成長していくこと
つまり ”和” を
明確な事よりも、ここち良く感じることができるのでしょう。
柱に亀裂を入れ隙間をつくる事
長い時間をかけて試行錯誤する
そうして築き上げた土台は2000年時を経ても実際に使える建物として生き残り続けるのでしょう。
同時期に建てられたローマのコロッセウムは観光地ではありますが、そこで競技することはできないのです。
式年遷宮の年が終わる今、無駄を無駄ににしない私たちの個性を改めて考えてみる今日この頃です。